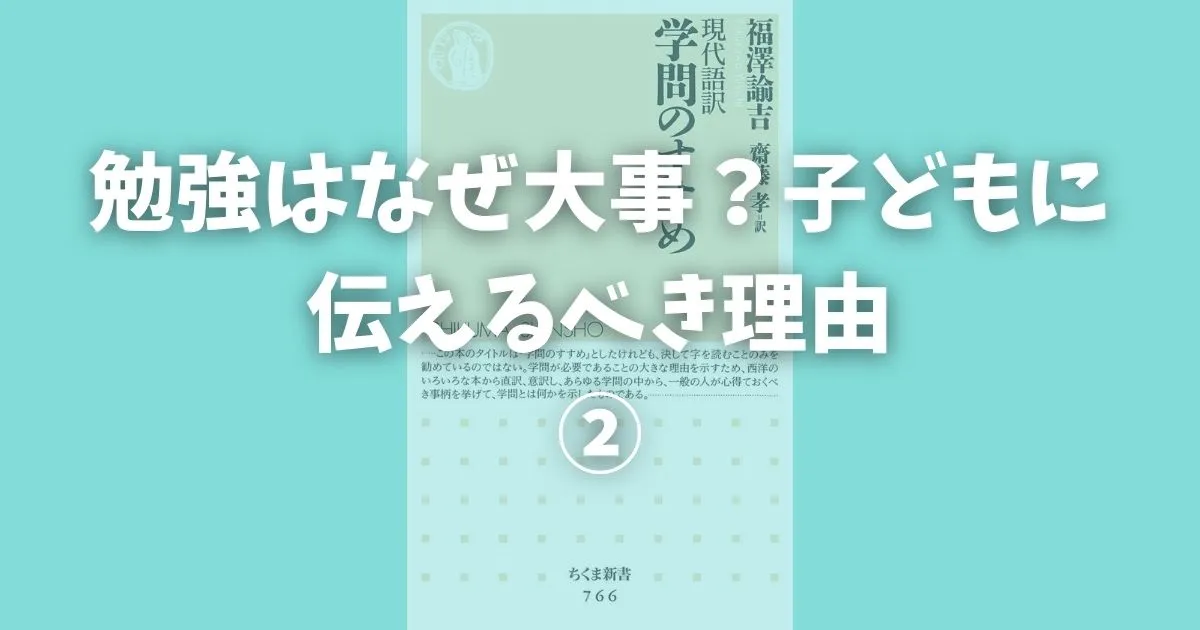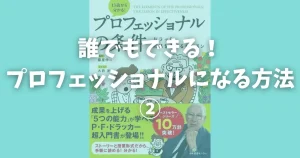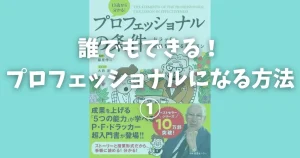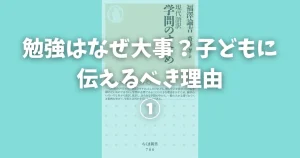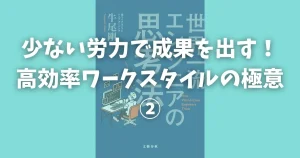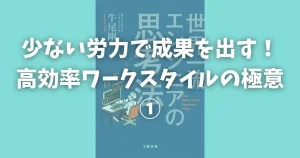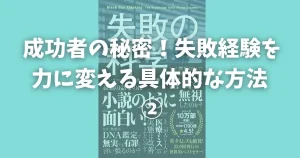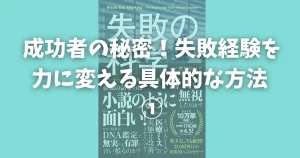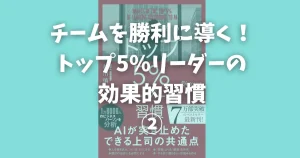みなさん、こんにちは今回は前回に引き続き福澤諭吉先生の「学問のすすめ」という本を解説していきます。
学ぶのは選択肢を広げるため
 はる
はる今日は前回に引き続き「学問のすすめ」の解説をやっていくぞ!



りょーかい。



次に勉強すると、いろんな職業に就けるようになるんだ。



弁護士や教師、薬剤師など、勉強しないとできない仕事がたくさんあるんだぞ。



選択肢が多いのがそんなに大事なの?



いい質問だね。考えてみて。



22歳から65歳まで働くと、一生で約825,000時間を仕事に費やすことになるんだ。



だから、仕事の選択肢が多いことは、人生の選択肢が多いことと同じなんだよ。



そうなんだ…。



でも、勉強ができることと、仕事ができることは別じゃない?



確かにそうだけど、社会に出たらまず、学力でふるいにかけられるんだ。



勉強を頑張れない人は、何も頑張れないと思われがちなんだよ。



じゃあ、勉強しないとダメなのかな…。



そうなんだ。特に、学生時代はどんな仕事に就きたいかを考える大切な時期だからね。



20歳を過ぎてからなりたい職業が決まった時、学力がないと就けない仕事もあるからな。
学ばないと「地位が低く、貧乏になる」



大人になってから「もっと勉強しておけばよかった」と思う人が多いって聞くけどどうしてなの?



その通り。そして、勉強しないと地位が低くなり、貧乏になるリスクもあるんだ。



福沢諭吉先生は、「人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言ったけど、これは学ぶか学ばないかで人生が変わるってことなんだ。



え、そういう意味だったの?



うん。そして、難しい仕事は高い地位の人がするもので、簡単な仕事は地位の低い人がするんだ。



その違いは、学問を学んだかどうかだけなんだよ。



勉強するかしないかで、そんなに大きな差が出るんだね…。



そうなんだ。だから、地位が低くて貧乏なのは、勉強しなかったからということを覚えておくといいよ。
ただ勉強するだけではダメ



そもそも学ぶって、数学や理科のことを指すの?



それも勉強だけど、もっと大切なのは学んだことをどう使うかなんだ。



難しい数学の問題を解くのもいいけど、それだけじゃないんだよ。



えっ、それじゃあ、何が大切なの?



例えば、工具の名前を知っているだけで家を建てられない大工みたいなものだよ。



大事なのは、学んだことを現実の生活や社会にどう活かすかなんだ。



なるほど、生活に役立つことが大事なのか。



そうだね。福沢諭吉先生も「実用性のない学問は後回しにして、普段の生活に役立つことを学ぶべきだ」と言っているんだ。



じゃあ、ゲームが好きなら、それをどう活かすかを考えるってこと?



その通り!学問はただの道具だから、それをどう使うかが大事なんだよ。



勉強すると、人生にいい影響があるんだね。



そうなんだ。勉強するとたくさんの人が集まり、選択肢が広がり、お金持ちになれるかもしれない。



そして、一番大事なのは、学んだことを現実社会にどう生かすかだよ。



今日の話、すごく役に立ったよ。これからも勉強しようと思う



それがいいね。人生で迷った時は、今回の話を思い出して。学び続けることが大事だからな。



りょうかい、ありがとう。



今回は、 福澤諭吉先生の「学問のすすめ」を解説しました。
本書では今回の解説以外にも為になる情報が紹介されているので、気になる方は是非、本書を読んでみてください。
まとめ
この記事では、勉強の真の価値と、それが私たちの人生にどのように役立つかを紹介しました。
勉強は、単なる学校の課題以上のものです。
それは、騙されないための道具であり、人望を得る方法であり、豊かな人生を送るための選択肢を広げる手段です。
また、実生活に役立つ知識を身につけ、現実社会での適用方法を理解することが大切です。
勉強は、未来への投資であり、それを通じて、より良い選択をする力を養うことができます。
学び続けることの重要性を忘れずに、自分の未来を切り開いていきましょう。



最後まで読んでいただき、ありがとうございます。



みなさん次回の解説も読んでくださいね!
記事が良かったらブログ作成の励みになりますので、みんなにシェアお願いします!